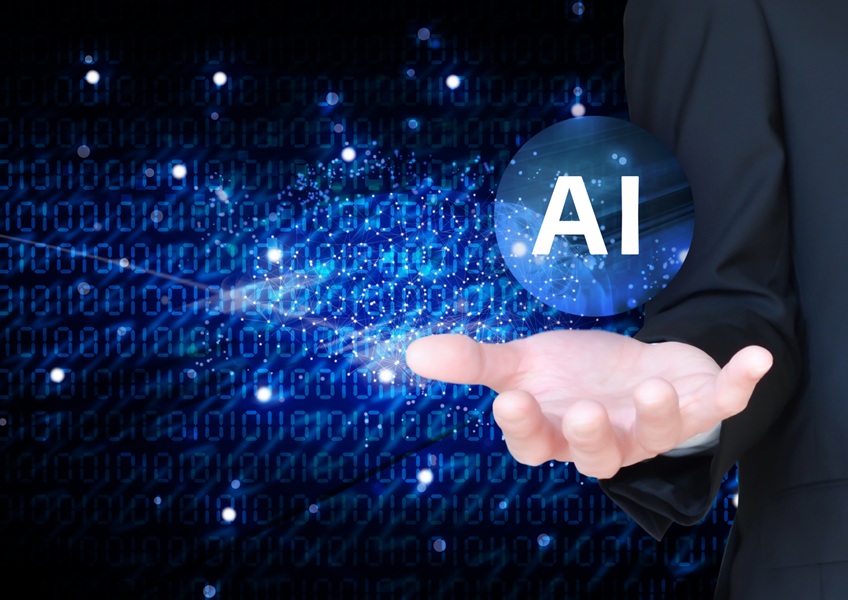
2025年上半期、訪日外国人の数が過去最高を記録しました。
その背景には、YouTubeやTikTokといったSNSで日本の魅力が容易に拡散される時代性があるといわれています。
進化しているのはSNSだけではありません。
近年、ChatGPTやDeepSeekなどのAI(人工知能)ツールも急速に進化を遂げています。
皆さんの中にも、何かしらのAIツールを使ったことがある方は多いのではないでしょうか。
「わからないことはGoogle検索」から、「まずはChatGPTに聞いてみよう」へ──
そんな時代の変化を、日常の中で実感している方も少なくないはずです。
Contents
AI翻訳で十分?必要なのは「信頼される翻訳」
翻訳の業界でも、AI翻訳の進化は目覚ましいものがあります。
品質も年々向上しており、以前のように街中で奇妙な外国語表記を見かける機会も減ってきました。
とはいえ、たとえばショッピングサイトやパンフレットなどで、「どこかおかしな日本語」や「違和感のある漢字表記」に出会い、思わず購入をためらった経験はありませんか?
ネットで誰でも簡単に買い物ができる今の時代だからこそ、「信頼」を得るための自然で的確な翻訳がますます重要になっています。
たとえ翻訳コストを抑えられたとしても、そこで生じる違和感や不信感は、顧客離れやブランドイメージの低下といった形で、将来のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
AIでは伝えきれない翻訳の本質
では、AI翻訳の進化により、翻訳業界そのものが消えてしまうことはあるのでしょうか?
翻訳者という職業は、今まさに窮地に立たされているのでしょうか?
答えは──Noです。
たしかに、Google翻訳やDeepLのようなAI翻訳ツールは、社内文書や日常的なメールなど、「意味が通じればよい」場面では非常に便利です。
無料で使えて、業務効率化にも貢献してくれる頼もしい存在です。
要は、「多少の間違いが許される範囲」なら、AI翻訳は有効に活用できるということです。
多少不自然でも、「AIで訳したんだろうな」と理解してもらえる場面では、実用性は十分にあります。
しかし──
「正確さ」「自然さ」「適切さ」が強く求められる場面ではどうでしょうか?
たとえば、小説や詩といった文芸作品の翻訳では、感情表現や文体、作者の背景にある文化的文脈を汲み取り、それを他言語で再現することが求められます。
これはまさに、人間だからこそ成し得る繊細な作業です。
また、マーケティング分野の翻訳──たとえば海外向けのウェブサイトや提案資料などでは、相手国の文化や慣習、使う場面に応じた言い回しやトーンの調整が必要です。
こうした「翻訳以上の配慮」は、まだAIには難しい領域です。
AI翻訳をそのまま海外マーケットに公開すれば、意図しない誤解を生んだり、企業イメージや信頼性を損なったりする可能性もあります。
AI翻訳の限界が最も顕著な分野
さらに、AI翻訳が最も入り込みにくい分野の一つが「論文翻訳」です。
とりわけ海外の学術誌に投稿する論文では、内容の正確さはもちろん、学術的文体や専門用語の使い方、分野特有の表現など、多くのルールに精通する必要があります。
では、「AIで翻訳して、そのあと人間がチェックすればいいのでは?」と思うかもしれません。
実際に、AI翻訳後の英文を人間の手で校正するという依頼は増えています。しかし、実はこれが想像以上に手間がかかる作業なのです。
AI翻訳には、文脈の誤解や不自然な言い回し、語調のズレなどが頻繁に見られ、それらを修正して自然で正確な文章に仕上げるには、大幅な修正と再構成が必要になることも少なくありません。
結果的に「最初からプロに頼んだ方が早かった」というケースも多く、逆にコストや時間が増えてしまう事態につながることもあります。
AIはツール、判断するのは人間
AI翻訳の進化は、これからますます加速していくでしょう。そして、それにともなって便利さも広がっていくはずです。
だからこそ、これからは「適材適所」の判断が何よりも重要になります。
目指すゴールにたどり着くために、何を使い、誰に任せ、どう活かすか──
それを見極められるのは、やはり人間です。
AIは強力なツールであり、共に歩むパートナーでもあります。けれども、「万能」ではありません。
その力を正しく使いこなすには、人間の判断と経験、そして想像力が必要です。便利さに頼りすぎるのではなく、あくまで「活用」する意識を持ち続けたいものです。
